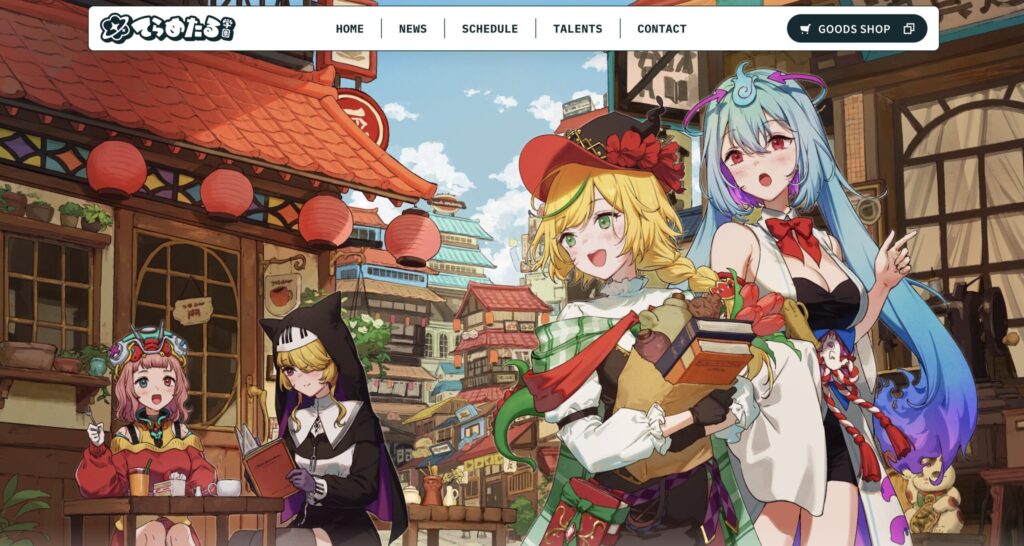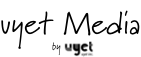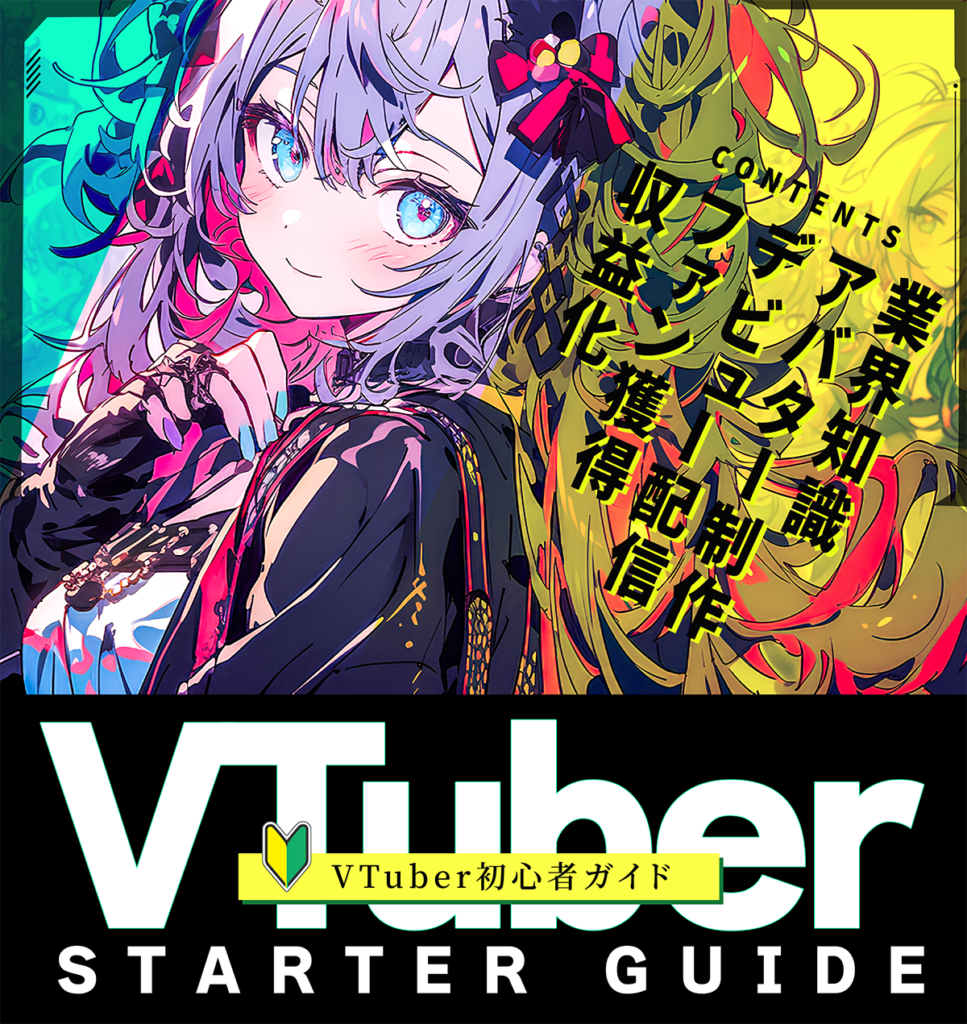キャラクターが生徒と同じ立場で悩みや挑戦を共有することで、“努力の物語”を日常的に配信できる。これにより、学習サービスの継続率向上やブランド親近感の醸成につなげている。
「MeSTAGE」は、配信・音源・コラボ・イベントなどを一体設計し、リアルとオンラインを横断する音楽ビジネスの新形態を構築。既存アーティストのライブ活動を補完しながら、新規層のファンとの接点を増やしている。
運営上は、既存の制作設備や流通ネットワークを活かし、立ち上げリスクを最小化。VTuberを“音楽IPの延長線”として運用し、LTVの多層化を実現している。音楽×VTuberの事例としては珍しく、既存事業との親和性と収益性の両立を果たしている点が特徴的だ。