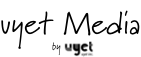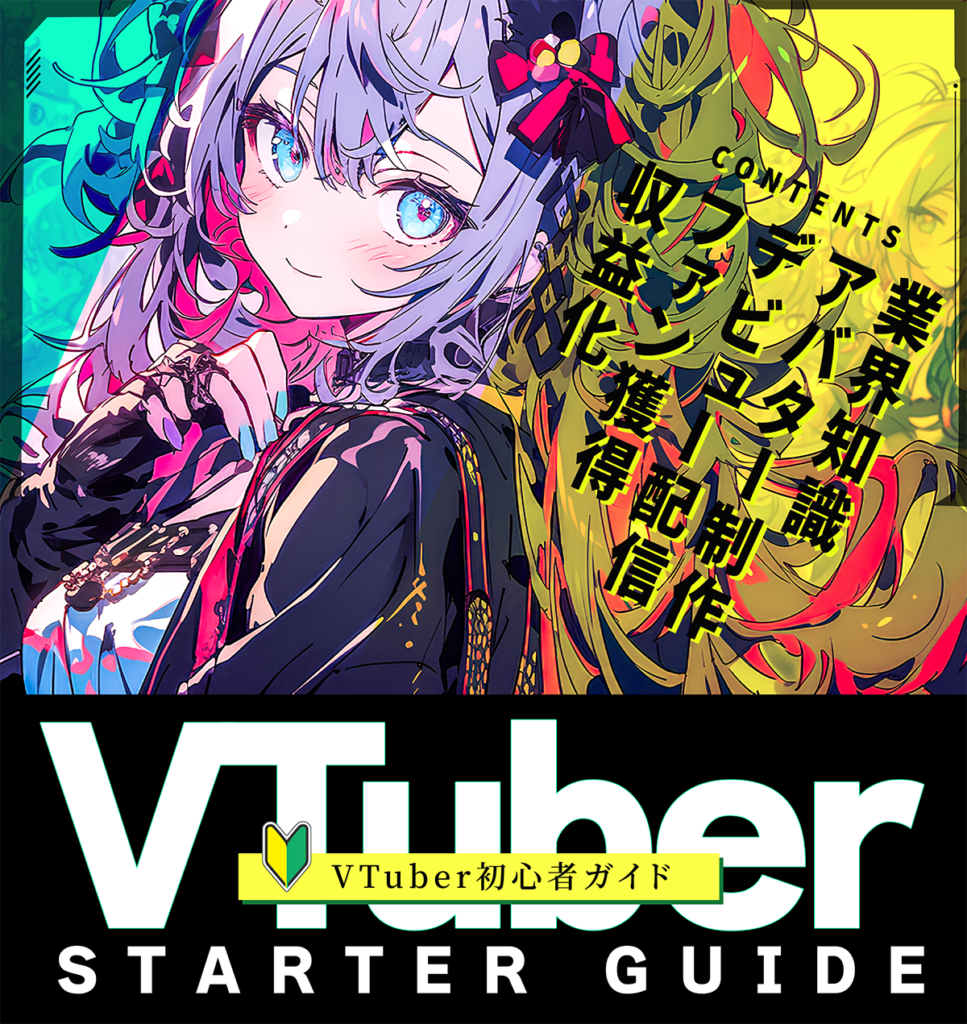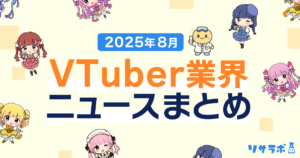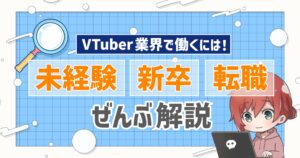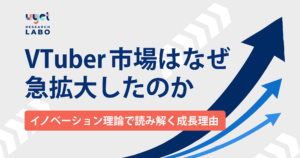2025年6月、VTuberプロダクション「にじさんじ」を運営するANYCOLOR株式会社が、2025年4月期の通期決算を発表した。
売上高は428億7,700万円(前年同期比+34.0%)、営業利益は162億8,000万円(+31.7%)と、またしても大幅な成長を記録。4期連続での増収増益を達成し、営業利益率は驚異の38.0%という高水準を維持している。
しかし、これらの数字を表面的に眺めるだけでは、この成長の中身──すなわち「何が伸びたのか」「どんな構造で利益が出ているのか」、さらには「この勢いは今後も続くのか」といった本質的な問いには答えられない。
本記事では、ANYCOLORの2025年4月期の決算資料をもとに、以下のような観点から企業の現在地と未来の輪郭を明らかにしていく:
売上・利益はなぜここまで伸びたのか?
どの事業領域が成長の牽引役となったのか?
収益構造は健全か、どこにリスクがあるのか?
ANYCOLORが描く中期戦略は現実的か?
加えて、物販の爆発的成長、ユニット展開の強化、EN事業の変調など、2025年度に見られた新たな兆しと、今後に向けた布石も読み解いていく。
読者がこの記事を読むことで得られるメリットは、「ANYCOLORの決算はすごい」と感じる“感覚”を、「なぜすごいのか、どこが勝負どころなのか」を“構造的に理解できる状態”へと変化させることだ。
にじさんじという巨大IPを軸に拡大を続けるANYCOLORが、どのような設計思想でビジネスを構築しているのか。本稿はその解像度を高めるための、決算分析レポートである。
第1章:ANYCOLOR決算で見えた“異常な強さ”の構造
売上・利益ともに前年比+30%以上。数字のインパクトを分解する
ANYCOLORの2025年4月期は、売上高428億7,700万円(前年比+34.0%)、営業利益162億8,000万円(+31.7%)という記録的な数値で着地した。
この成長率は、一般的な上場企業の水準を大きく上回るどころか、同じIPビジネスを展開する大手VTuberプロダクション「カバー株式会社(ホロライブ運営)」と比較しても一歩抜きん出ている水準である。
注目すべきは、売上・利益ともに「成長」と「高収益性」の両立ができていることだ。営業利益率は38.0%。VTuber業界の黎明期に比べればコンテンツ投資やスタジオ費用も大きくなっているはずだが、マージン構造は依然として極めて高い。これは、ANYCOLORの事業運営が「配信タレント事務所」ではなく、「IPコンテンツホルダー」に進化していることを示す。
通期の成長もさることながら、四半期推移にも注目したい。
Q1(5〜7月):74.3億円
Q2(8〜10月):99.1億円
Q3(11〜1月):115.6億円
Q4(2〜4月):139.7億円
と、Q2→Q3→Q4と連続して更新し続け、Q4は前年比+60.2%という爆発的な伸びを記録。四半期ごとに着実に“売上の階段”を上がっている点は、偶然ではなく、意図的な商品設計とスケジュール管理の賜物だと考えられる。
全社成長のドライバーは「コマース」一強。異例の偏重構造
この爆発的成長の原動力は、紛れもなく「コマース」領域である。売上構成を見ると以下のとおり:
- コマース:278.4億円(前年比+47.0%)
- ライブストリーミング:50.6億円(横ばい)
- イベント:28.2億円(+48.0%)
- プロモーション(企業案件など):66.5億円(+25.2%)
実に全体売上の65%を物販が占める“物販に強いIP企業”といっても過言ではない構造となっている。
また、コマースは四半期ごとの変動が大きいにもかかわらず、平均して右肩上がりに推移している点がポイントだ。特にQ4では「にじさんじ7周年」や台湾ポップアップなど大型企画に加えて、ボイスやぬいぐるみ、記念グッズの売上が過去最大規模に。SKU数は年間4,932点、月あたり約400点の新商品を投下する施策体制は、IPを軸としたコマース企業の中でも突出している。
一方で、ライブ配信領域は売上横ばいで微減傾向にあり、スパチャの機会が上限に近づいていることが影響していると考えられる。今やANYCOLORのライブは「ファンのプロダクションとの接点作り」であり、「収益機会」ではない。こうした構造の割り切りと、コマースを軸にした運営が、事業収益性を押し上げている。
好業績の裏で高まるコスト圧。利益率に忍び寄るリスク
一方、強気な成長の裏では“コスト構造の変化”という兆しも現れている。
まず変動費率(=売れた分だけかかるコスト)を見ると、前年46.1%→本年46.4%と微増。理由は、イベント比率の上昇に加え、ぬいぐるみなどリアル商品の製造・管理コストが増加傾向にあるためと考えられる。
次に販管費(人件費・外注費・オフィス費用など)も急増。
- 前年:28.4億円 → 本年:38.3億円(+34.6%)
なかでも人件費は19.5億円 → 33.7億円(+72.9%)と急増しており、スタジオ投資や100名超の新規採用を行った影響が顕著に表れている。
利益率は全体では維持されているが、「売れているから利益が出ている」状態であり、固定費は着実に重くなっている。今後の成長鈍化局面では、この固定費構造が利益率を圧迫する可能性もあるため、コマース施策の精度維持が不可欠だ。
Q4に何が起きたのか?物販とイベントのブースト
2025年Q4はANYCOLORにとって、歴代最高の四半期業績となった。売上139.7億円(+60.2%)、営業利益53.1億円(+60.0%)という驚異的な数字を叩き出している。
この背景には、「にじさんじ7周年」と「にじさんじフェス2025」という大型イベントの開催がある。加えて、ボイス・定常販売グッズのラインナップが想定以上にヒット。台湾でのポップアップストアの反響も想定を超えたという。
特にコマース領域では、「周年」「ユニットごとの記念施策」「ボイス施策」「ぬいぐるみ」の四段構えでファン層に刺さるコンテンツを配置。イベントでは、ネットチケットの“後伸び”が想定を上回ったとされ、ファン熱量の蓄積とコンテンツ体験価値の最大化が合致した結果だといえる。
このように、「勝負をかけた企画が計画を超えてヒットした」というのがQ4成功の本質であり、偶然ではない。Q4は、ANYCOLORが持つ「スケジュール・グッズ・配信・リアルイベント」すべての武器が完璧に機能した象徴的な事例である。
VTuber数の増加とともに変化する収益分布図
期末時点の所属VTuber数は170名(前年比+12名)。
そして重要なのは、収益貢献度が上位25名で50%以上を占めているという点だ。
これは人気格差が大きい一方で、「収益化できるVTuber」を確実に育成できている証拠でもある。
また、2025年度はVTA(バーチャル・タレント・アカデミー)出身を含めて19名が新規デビュー。通常のオーディションに加えて、「ペア」「女性ゲーマー」「男性アイドル」などテーマ別オーディションを実施しており、ジャンルごとの“市場開拓”を戦略的に行っていることが読み取れる。
ANYCOLORのモデルは、“全員で同じ配信文化を広げる”というより、「多ジャンルで小さなコミュニティを複数成立させていく戦略」だ。この構造が、物販との相性を生み出し、全体のエンゲージメントと売上の安定性に寄与している。
第2章:コマース偏重モデルの強さと限界
「にじぱぺ」だけじゃない。月単位で施策を打ち続ける販売体制
ANYCOLORの決算から明らかになるのは、にじさんじの“物販に強いIPコンテンツホルダー”とも言える構造である。コマース領域の売上は278億円を超え、全社売上の65%を占めている。つまり、ANYCOLORという会社は、もはや「配信収益に頼らないVTuberグッズ企業」なのだ。
とはいえ、ここで誤解してはならないのは、「たまたまヒット商品が出た」から売上が膨らんだのではないという点だ。2025年度のグッズ施策は年間で190件、SKUベースでは4,932点に達しており、平均すると月に400点以上の新商品を投入している計算になる。
これはライブや周年といった特別なタイミングに依存せず、常時“何かが発売されている状態”を維持する運営体制が確立されているということを意味する。ボイス商品や定番グッズ、記念日施策など、施策軸と販売スケジュールが戦略的に網の目状に敷かれており、「このファンにはこれが刺さる」と狙い撃ちする企画力が、単なるキャラ人気ではなく“設計された売上”を作っている。
SKU4,900点超。爆発的な施策数と、その設計思想
ANYCOLORの物販施策には大きく分けて6つの系統がある:
- 定番グッズ(アクリルスタンド、缶バッジ等)
- コンセプトグッズ(ぬいぐるみ、デフォルメなど)
- 季節イベント連動(ハロウィン、バレンタイン等)
- 記念日系(誕生日、周年など)
- イベント連動グッズ(ライブチケットと連動)
- デジタル系商品(ボイス、サイン、AR等)
これらを年間通して織り交ぜながら、ファンの“購入動機”を月単位で刺激し続けるモデルが取られている。
例えば、ぬいぐるみ関連施策は「にじぱぺ」などのキャラクターグッズに加えて、2025年4月にはリアル常設店舗「にじさんじ ぬいストア」を横浜にオープン。同時にオンラインでは「ぬいポータルサイト」も展開し、リアルとデジタルを統合した物販導線の強化に踏み切った。
このような仕組みは、単なる在庫販売ではなく、「企画→製造→販促→回収」までを内製または密接にコントロールする体制がないと成立しない。ANYCOLORはこれを「IPマーケティング本部」「プロデュース本部」「ビジネスマーケティング部」といった部署に分解しており、IPの一気通貫マネジメント体制が強さの根底にある。
実店舗・Live2D・PV活用まで。IPグッズプロモーションの最前線
にじさんじグッズの販売体制は、単に「グッズを売る」だけでは終わらない。むしろ、“売るための演出”にコストと労力を惜しまない姿勢こそが、他社との差別化要因となっている。
具体的なプロモーション手法としては以下が挙げられる:
- グッズ紹介のLive2DアニメPVの活用
- 販売中グッズをライブ配信で実装・紹介
- 特設サイトで世界観を表現
- SNS連動キャンペーン(Xなど)
- オフライン展開:ポップアップストア/常設店/海外展開(台湾など)
また、制作面でも品質・供給体制の安定を重視し、製造委託先の分散管理や品質ガイドラインの運用、リリースタイミングの厳格な管理といった仕組みを敷いている。
これは裏を返せば、VTuber事業でありながら「商社的機能」と「D2Cブランド的運営」を内包しているということにほかならない。キャラだけでは売れない、仕掛けがないと動かない——そうした現実に向き合って作り込まれた物販体制は、ANYCOLORの最大の武器となっている。
収益最大化を支える「製造管理」と「商品ライン設計」
このグッズ構造をもう少しビジネス視点で見ると、以下のような最適化ロジックが見えてくる:
- 単価の高い限定品(周年・受注生産)で荒利を確保
- 定番商品でキャッシュ回収の安定性を確保
- 月ごとのファン層・属性に合わせて絞り込んだライン設計を行う
- 季節性や話題性を活用した“短期集中の施策”でブーストを狙う
この設計は、新規顧客の獲得と既存顧客のロイヤルティ強化の両立という、D2Cマーケティングの王道と重なる。
たとえば「誕生日施策」などは、VTuber個人ごとに行われるため、販売点数としては小さくなるが、ファンの熱量は最も高い。「推し活」としての感情消費が促されやすい分、利益率は非常に高くなる傾向がある。
逆に「にじさんじフェス」や「周年」などの全体施策は、認知層の広がりに寄与し、ライト層・箱推し層を巻き込む入口施策として機能する。商品ラインの幅と売上重心の調整により、リスクヘッジしながら高収益を維持する運営構造が成り立っているのだ。
だがグッズは水物?季節性と施策依存のリスクも見逃せない
一方で、当然ながらグッズビジネスには“水物”特有のリスクもある。
- 企画の当たり外れが激しい
- 製造リードタイムの長さと販売時期のズレ
- ファンの可処分時間・可処分所得の取り合い
- サステナビリティ(物理在庫の管理、環境面)などの社会的視点
実際に、ANYCOLORの四半期売上を見るとQ1→Q2→Q3→Q4と伸びてはいるが、施策が乏しい月には前年比割れしている局面も存在する。安定しているように見えて、実態は「仕掛けを打ち続けなければ維持できない」構造なのだ。
これは言い換えれば、「好調なときは一気に収益を押し上げられるが、失速したときの影響も大きい」というモデルでもある。実店舗や新規展開が増えるほど固定費も積み上がるため、企画の設計精度と売上予測の制度は今後ますます重要になる。
第3章:にじさんじならではのIPの育て方
ユニット展開×ライブイベントで「にじさんじ全体」の熱量を演出
にじさんじが他社IPと大きく異なる点のひとつが、「VTuber個人」ではなく「ユニット」や「全体企画」を軸にしたIP設計である。
ANYCOLORの2025年4月期決算でも、ライブイベントやプロモーション領域での戦略においてこの傾向がはっきりと読み取れる。
たとえば、2025年2月に開催された「にじさんじフェス2025」では、イベントホールでの6公演を含むリアルイベントに加えて、着ぐるみショーやアトラクション、展示、企業出展なども同時に実施。さらに、「前夜祭・後夜祭」のネットチケット販売が開催後に大きく伸びたという報告もあり、“ライブ体験”がファンの熱量を高める機会として機能したことがわかる。
また、ユニット単位での音楽リリースや番組展開も進んでおり、複数人をセットにしてファン層を拡張していく動きが活発化。これは、1人の人気に依存せず、構造的に熱量を維持・成長させる仕組みと言える。
にじさんじはもはや「配信者の集合体」ではなく、“生きているIP群”としての集合体になっている。
VTA発・19名の新星を輩出。育成型IPとしての仕組み
2025年4月期には、ANYCOLORが運営する「バーチャル・タレント・アカデミー(VTA)」からのデビューを含め、年間19名の新規VTuberがデビューしている。
VTAは、2021年6月に立ち上がった育成制度であり、オーディション合格者に対して数ヶ月〜1年程度の研修期間を設け、配信スキルやマインドの醸成、機材操作、コンテンツ設計などを行う仕組みだ。
このモデルの最大の特徴は、育成段階をオープンにし、研修生の姿をリアルタイムでファンに届けている点だ。デビュー前からファンとの接点を構築し、IP価値の醸成を始めるこの方式は、ANYCOLORならではの育成型IPモデルと言える。 このモデルは、従来の「配信者をスカウトしてキャラを与える」方式とは異なり、ANYCOLORがIPの企画〜人材の育成までを垂直統合的に行う戦略だと言える。
さらに、2025年度は通常のオーディションに加え、
- ペアオーディション
- 男性アイドルオーディション
- 女性ゲーマーオーディション
- U-21向け育成枠
といったテーマ別の募集を複数回開催しており、「戦略的にジャンルを切り分けてファン層を獲得していく」という意図が透けて見える。
VTAの累計応募者は2025年4月期時点で約4.1万人に達しており、これは単なる育成機関ではなく、“ファンごとIPを生み出す土壌”として機能しはじめている。
「歌謡祭」「甲子園」「麻雀杯」――VTuberが掛け算になるコンテンツになる瞬間
にじさんじのIP展開において特筆すべきは、「ライバーの活動そのものがコンテンツ化されている」という点だ。
たとえば、2025年度に実施された大型企画には以下のようなものがある:
- にじさんじ甲子園(ファン参加型eスポーツ実況)
- にじさんじ歌謡祭(音楽ライブ+CDリリース)
- にじさんじ麻雀杯(タレント参加のトーナメント企画)
- Mario Kart/マリオカート杯(対戦イベント)
これらはいずれも、「VTuberのキャラクター性×競技性/感情の起伏」を掛け合わせた人気フォーマットであり、ライブストリーミングを基軸にしながら、イベントやコマースに“再利用可能な熱量”を蓄積していく構造を持つ。
結果として、VTuberは「ただ歌って配信する存在」ではなく、“物語の演者”としてファンの中でストーリーを生きる存在へと拡張されていく。
この「共通体験を持ったIP構築」という思想が、ANYCOLORにおける事業成長の核となっている。
エンゲージメントとブランド構築に分かれた戦略設計
興味深いのは、ANYCOLORが明確に“エンゲージメント施策”と“ブランド構築施策”を分けて設計している点である。
- エンゲージメント重視の施策
→ にじぱぺ、ボイス、誕生日、日常系グッズなど
→ ロイヤルユーザー向けに高頻度で設計 - ブランド拡大・ファン層拡張重視の施策
→ にじさんじフェス、企業コラボ、アニメタイアップなど
→ ライト層・未接触層への認知拡大を狙う
このように、事業部門ごとにKPIの軸が明確化されており、それぞれがVTuberというIPを“手段として最適に使い分けている”点は、戦略設計として非常に高度だ。
IPの価値を一過性で消費するのではなく、ファンの接触頻度と文脈をコントロールしながら、長期的にエンゲージメントを築くという意図が、企画の粒度と種類から伝わってくる。
ホロライブとは違う「マス依存しない運営構造」
VTuber業界のもう一つの巨頭「ホロライブ」と比較すると、ANYCOLOR(にじさんじ)はそのビジネスモデルにおいて明確に異なる戦略を採っている。
| 観点 | にじさんじ(ANYCOLOR) | ホロライブ(カバー) |
| ビジネス軸 | 物販・イベント・案件の多面展開 | ライブ・メンバー人気主導 |
| ファン層 | コア〜中間層の共存 | ロイヤルファン偏重 |
| 施策構造 | ユニット×季節イベント×多品種物販 | ソロ×大型ライブ中心 |
| 配信頻度 | 平均して安定した稼働 | タレント依存度が高い傾向 |
| 成長ドライバー | 設計されたD2Cと育成プロセス | スター人材と外部展開(アニメ等) |
にじさんじは、「箱推し」や「文脈ファン」の存在を前提に設計された“群像劇型IP”だ。
そのため、タレントが卒業してもファン層が崩れにくく、代替性のあるイベントや施策を柔軟に再構築できる。これは“ファンのLTVを最大化するIPホルダー”とでも言うべき考え方だ。
こうした育成型・構造設計型のIP戦略は、エンタメ業界の他領域にも応用可能であり、にじさんじは今や「VTuber」という枠を超えた“成長可能性のある仕組み”として確立しつつある。
第4章:事業成長の陰に潜むリスク要素
人気VTuber依存の懸念はあるのか?収益の分散構造を検証
VTuberビジネスにおける常套的な懸念として、「一部の人気VTuberに収益が依存しているのではないか?」という問いがある。
この疑念に対し、ANYCOLORは決算資料で明確なデータを提示している。
FY2025/4の収益データを見ると、上位25名のVTuberで全体売上の約50%を構成している一方、26位〜100位までは収益への貢献度が急激に下がり、0.6%〜0.2%レベルにとどまっている。つまり、“エース層”が事業を牽引し、ロングテールは現時点で大きな収益源ではないというのが実情だ。
この構造をどう評価するかは難しい。依存リスクと見るか、エース層の投資効率の高さと見るか。重要なのは、下位層が“ゼロではない”ことと、育成プロセス(VTA)により新陳代謝が機能している点である。
事実、FY25/4期には19名の新規デビューがあり、デビュー直後の収益貢献が早期化している傾向も見られる。“育てて稼がせる”までのスピードが上がっている点は、単なる依存構造ではなく「代謝可能な構造」への進化を意味する。
人件費急増とスタジオ投資。固定費構造の変化
業績好調の裏でじわじわと存在感を強めているのが固定費の積み上がりだ。
2025年度の販管費は38.3億円(+34.6%)であり、その内訳を見ると人件費が33.7億円(前年19.5億円)とほぼ倍増。新スタジオの開設や100名超の新規採用がその背景にある。これにより、VTuberプロデュースやマネジメント、コンテンツ制作、営業、デザイン、エンジニア部門などを含む“IPコンテンツホルダー企業”としての体制が大きく拡大している。
また、新スタジオ投資(23億円超)はキャッシュフロー上ではすでに反映済みだが、減価償却やオペレーションコストとして今後の四半期にじわじわ効いてくる可能性がある。
こうした構造変化は、「売れているうちは問題ない」が、イベントやコマース施策の精度が下がった場合に収益が耐えられるかという観点で見る必要がある。これは、成長フェーズから安定フェーズに移行した企業に共通する“スケーラビリティリスク”であり、まさに今がその分岐点にある。
「全員が稼げる」わけではない。収益貢献の偏り
VTuber数の増加(期末時点で170名)に対して、実際に収益を大きく上げているのは上位数十名のみという構造は、今後の課題でもある。
当然ながら、全員が均等に売れるということはあり得ない。しかし、下位層の稼働率やエンゲージメントが低下すると、ファン離れや運営負荷の集中、マネージャー工数の非効率化といった副作用が生じる可能性がある。
ANYCOLORはこの課題に対し、以下のような分散設計を試みている:
- ユニット編成による集団での活動機会の付与
- 多品種・小ロット販売による下位層でも刺さる商品の設計
- テーマ特化のオーディションで個性に応じた市場の創出
このように、下位層を“脱落させない”ための“参加可能な場所”を設計している点は評価に値する。とはいえ、根本的な課題は「人気が可視化されやすい構造」であり、それに起因するモチベーションや視聴数の格差である。
収益貢献度が偏っていることは事実だが、それを“問題”にしない運営設計こそが、今後のキーポイントとなるだろう。
中国・EN領域の停滞。ローカル化戦略は再構築フェーズへ?
FY2025/4では、「NIJISANJI EN」の売上が前年比45%減(48.6億円 → 26.5億円)と、大きく縮小している。特にQ4では、グッズ・配信・案件いずれも前年を下回る着地となっており、明確に苦戦が表面化している。
また、中国・韓国・インドネシアといったグローバル拠点も、現在は事実上の縮小状態にある。グローバル売上(EN含む)はFY23/4では全体の約25%を占めていたが、FY25/4では全体の10%以下まで低下している。
この背景には、EN市場での競争激化(VShojoやホロENなど)や、現地のライバー支援体制の薄さ、文化摩擦、コンテンツ設計の齟齬など、複合的な要因に加えてがある、2024年に所属ライバー・セレン龍月を巡る一連の炎上騒動も一定の影響を与えたと見られる。
騒動の経緯については、ANYCOLORが契約解除とその理由を公式声明として公表しており、SNS上での発言や運営との対立を含む内容が注目を集めた。英語圏を中心に大きな反響を呼び、一部ファンコミュニティでは運営への不信感やライバー活動への関心の低下も見られた。
ANYCOLORは中期的に海外市場を再度強化する姿勢を見せているものの、現時点では“グローバル展開は一度立ち止まり、再構築フェーズに入っている”と見るのが妥当だ。
今後の海外戦略には以下のような対応が求められる:
- ローカル制作・マネジメントチームの強化
- 言語・文化に応じたIP設計の柔軟化
- 「輸出」型から「現地起点」型への転換
特に、日本市場で成立しているビジネスモデルをそのまま展開するだけでは限界がある。今後はENをはじめとするグローバル領域が、再び成長ドライバーになり得るかどうかが問われる局面に入る。
第5章:中期成長目標+注目すべき次の一手
「売上+88%・営業利益+94%」の中期計画は実現可能か
ANYCOLORは、2025年6月の決算発表と同時に中期経営目標(FY27/4期)を開示している。数値目標は以下の通りだ。
- 売上高:600億円(FY24/4期比+88%、CAGR約23%)
- 営業利益:240億円(+94%、CAGR約25%)
- 営業利益率:現行38%前後を維持する想定
この成長率は、単なるストレッチ目標ではなく、構造的な裏付けがある数字設計といえる。というのも、同社はFY25/4においてすでに下記の成果を挙げているからだ。
- コマース領域の成長率:前年比+47.0%
- VTuber数の純増(19名デビュー、計170名)
- EN市場を除く国内領域の四半期売上は継続成長中
- 各ユニットによる施策の定着化
つまり、「既存領域の延長線+再強化されるEN・新規IP領域」で、600億円ラインは現実的に狙える範囲である。
ただし、利益率の維持に関しては、人件費や設備投資による固定費増が今後の重荷になりうるため、成長の質が問われることになる。
拡張の鍵は“育成”と“ユニット”。VTAと音楽戦略に注目
今後の事業拡張において、ANYCOLORが注力すると明言しているのが、
- VTA(バーチャル・タレント・アカデミー)による人材供給
- ユニット活動の強化と音楽展開
の2点である。
前者は、すでに年間19名の新規デビュー(VTA出身含む)を実現しており、FY26/4以降も年平均10〜15%の新規輩出を計画している。オーディションの幅も「ペア/女性ゲーマー/男性アイドル/U-21」など、マーケットに対して明確なセグメント戦略を打ち出している点が特徴的だ。
後者のユニット展開は、FY25/4においても複数のユニットがオリジナル楽曲の制作・ライブ出演・グッズ展開を行っており、“パーソナルIP”から“ユニット型IP”へのリスク分散と価値拡張の流れが加速している。
特に、音楽分野においては3Dライブ・CD販売・Blu-ray・グッズ・チケット販売などの複合的収益が可能なため、収益性が高く、ブランド価値の向上にも寄与する。
これは、VTuber事務所であると同時に、「メディアミックスIPの育成企業」であるというANYCOLORの立ち位置を明確に示すポイントでもある。
EN/海外再拡大とメディアミックスは次の柱になるか
一方、足元で停滞が見られたグローバル領域(ENや中国等)についても、ANYCOLORは再強化の方針を明確にしている。
これまでの反省を踏まえ、今後の海外展開では以下のような構造転換が求められる:
- 「輸出モデル」から「現地起点のIP設計」へ(ローカル市場に適応したライバー・企画・商材設計)
- 現地マネジメント/制作チームの強化
- 海外パートナー企業との協業/ライセンス展開
特に注目すべきは、「EN市場でのアニメ・ゲームタイアップ」「海外向けぬいストア」などのメディアミックス+物販戦略である。これはコマース領域で培った強みを国外に移植する第一歩とも言える。
また、直近では大手企業とのコラボ(例:三菱UFJ銀行、くら寿司、エースコックなど)も相次いでおり、国内外を問わず“リアル接点のあるコンテンツビジネス”として、IP拡張の基盤を築き始めている段階にある。
ANYCOLORの経営哲学と、変わらぬ「着実な攻め」
ANYCOLORの事業運営を貫いているのは、派手な打ち上げ花火ではなく、「再現性あるスケーラブルな仕組み」を積み重ねる設計的な思考である。
- 毎月400SKUを出し続ける物販設計
- VTAを通じた年20名近いVTuber供給体制
- ユニット・イベント・企業案件を重層的に絡めるプロデュース戦略
こうした一貫した「積み上げ型」の戦略こそが、業績の裏側にある本質的な強さだ。
これは、数人のタレントに依存するビジネスとは全く異なる思想であり、エンタメ企業としての“持続可能性”と“多面展開可能性”を内包したモデルである。
VTuber市場が成長から再編・淘汰のフェーズに入る中で、ANYCOLORの経営は「仕組みで勝ち続ける」ための基盤整備を着実に進めている。今後、これにどう“物語性”や“新領域のIP”が掛け合わさるかが、次の注目ポイントとなるだろう。
まとめ:ANYCOLORの強さは「仕組み」にある——次に読むべき記事
2025年4月期決算を通して明らかになったのは、ANYCOLORが単なるVTuber事務所を超えて、“生きているIPコンテンツホルダー企業”として進化を遂げているという事実である。
年間売上は428.8億円、営業利益は162.8億円と、驚異的な数値を叩き出しながらも、その成長は「一発屋的ヒット」ではなく、物販・イベント・育成・ユニット・育成といった“複数の仕組みが連動した結果”として成立している。
同時に、固定費構造の変化やグローバル展開の再設計といった、今後の成長を左右する重要な論点も浮かび上がった。
にじさんじの戦略を理解することは、今後のVTuber・IPビジネスの未来を読み解く上でも欠かせない基盤となる。